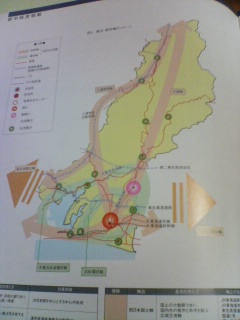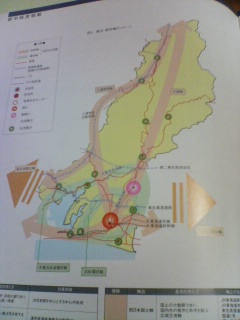
議会が終わったので、今週はすこしその後片付けと言うか、取り急ぎ自宅とPCでの書類整理をしています。あわせて議会中にお申しでいただいた案件で、議会中につき処理できなかったものを少しずつ対応しています。
さて、行革審の秋山さん(あれ?まだ本決まりではなかったんでしたっけ?)からご質問をいただいた三遠南信の件で、すこし補足の説明をさせていただきたいと思います。
三遠南信自動車道は、政治に詳しい人の言葉を借りれば、「熊谷代議士の忘れ形見」とも言われている、北遠地域活性化の期待がある高規格道路(高速度で移動可能な自動車専用道路)ですね。
熊谷さんは静岡県でも有数の実力派議員と言われていましたが、いろんな理由で落選・引退されました。実際、ここまでの大規模プロジェクトを地元に引っ張ってきたのですから、相当な政治力があったのでしょう。私も何度もお話させていただいたことがありますが、構想の大きさを感じる方でした。
道路としては、第二東名の引佐ジャンクションから長野県の飯田までの区間です。第一東名と第二東名の取り付け道路をあわせると、三ケ日から飯田までを結ぶことになります。
写真のとおり、浜松市の総合計画の中でも、都市経営・都市形成の前提となっている道路ですが、とくに北遠地域の活性化効果となると、私は費用対効果を考えると、個人的には疑問だと思っています。(北遠の方、特に事業協力された方には大変失礼で申し訳ありませんが、あくまで事業そのものの評価としてです)
総事業費は約5000億円。特に浜松市は政令市になりましたから、浜松市を通る部分については地元負担が発生し、それは確か3分の1だったと思います。おそらく地元負担だけで200~300億の規模でしょう。(未確認ですので間違っていればおゆるしください。)
静岡空港の本体部分が500億円、周辺道路整備費や代替農地などの周辺事業も入れて1900億円ですから、いかに巨額の事業かと言うことがわかると思います。
現在は市内部分(佐久間~水窪間)については既存道路をグレードアップ(高架ではなく、拡幅などで高速化する)する方式になり、いま鳳来から佐久間に向けてのトンネルを掘っている段階だと記憶しています。残念ながら、まだこの道路の現場を見に行ってもいないので、あまりリアルな情報をお伝えできません。申し訳ありません。
で、本質論、原理原則論から行くと、秋山さんがおっしゃっていることはまさにそのとおりで、皆さんの税金を使う公共事業ですから、秋山さんのような視点で徹底的にコストや事業のあり方を見直さなければならないと思っています。
そういう視点から見ると、三遠南信道路にはいろんな問題があります。
まず、路線。これは地図を見ていただければと思うのですが、たしかにくねくねしています。無理に北遠を通しているような感じを受けると思います。それについては、そのとおり。明らかに無理に通していますね。
この辺の山脈には、小学校の地理で習った、中央構造線が通っています。フォッサマグナと中央構造線は習いましたよね。つまり断層地帯なんですね。そこを引佐から鳳来にぬけるためにいったんトンネルでくぐり、鳳来から佐久間に戻るためにもう一度トンネルでくぐり、そして水窪から長野県にはいるのにもう一度トンネルでぬける。断層地帯の中央構造線をわざわざ3回もまたいでいるんですね。
つまり、この巨額の事業費は、トンネル堀り賃なんです。それがつみあがって大きくなっている。
おそらく路線を見直せば、ここまでの事業費にならなかったでしょう。しかし逆に言うと、見直していたら、衆議院静岡7区をはじめ多くの選挙区をとおらなければ、事業化されなかったかもしれません。それは政治的理由と、地元負担の負担者が多ければ多いほど割り勘になると言う財政的事情です。こればっかりは、今の私の立場ではわかりません。
その結果、事業は遅れ、事業費は増えることになります。
また、地域の活性化効果や、接続による移動時間短縮と移動量増加による経済がどのくらいはたらくかというと・・・私は疑問を持っていますが、諸説ありますね。
ただひとつ例を申し上げると、「ストロー効果」というものがあります。
これは私は市議時代に北海道の小樽に行き、小樽の行政関係者や地元商店、旅館の方々に実態を聞いて確認してきたのですが、高速道路ができて地元経済、とくに旅館業はすさまじく疲弊したと言う例があります。
高速ができて都市まで1時間とかになると、まずその地域には泊まらなくなります。日帰りになるんですね。また、すぐにいけるとなると、旅行先としての魅力もだんだん低下します。お手軽になりすぎて、ありがたみがなくなると言うことです。とうぜん、お土産も売れなくなります。
あわせて、これまで支店などを置いていた会社も、すぐにいけるからそれを閉鎖する。こうしたいろんな事象が積み重なって、結果的に高速道路がストローのように田舎から都市へあらゆるものを吸い上げてしまう。これがストロー効果です。
私は、これら二つの点で、三遠南信には多くの課題・問題があると思っていますが、当時こうした意思決定に参加できる立場ではなかったので、今となってはどうすることもできないのが実態です。
一方で途中までできていながら供用しないとなると、それこそ単純な無駄になります。先日おなくなりになった宮沢元首相などのケインジアンによると、穴を掘ってまたそれを埋めても経済効果があるとのことですが、私は国家財政の現状や公共事業の効率性などを考えるとそれはないだろと思っているので、だいぶ進捗している以上、一刻も早く効果現出を狙うべきだとも思っています。(とはいえ、その効果と言うものが、さきほどのストロー効果なら、まったく意味がないのですが・・・)
今度一度現地に行って、工事の進捗や予定区間の様子などを見てこなければならないと思っています。やはり政治は現場で起きています。7月議会も終わったので、こうした現地調査のほうも力を入れて進めて行きたいと思っています。同時に、お忙しい皆様には、私自身が自分の目で見た生の情報をお伝えできるようにしたいと思っています。

 行政・自治体| 浜松市|
行政・自治体| 浜松市|